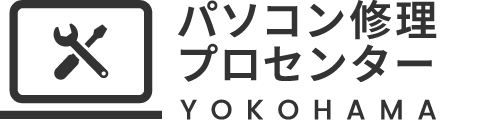BIOSアップデートは必要?適切なタイミングやメーカー別のアップデートする方法を徹底解説

BIOS(バイオス)は、パソコンの起動や基本的な動作を支える大切なシステムです。しかし、多くのユーザーにとってBIOSは普段あまり意識しない存在であり、アップデートの必要性や手順についてもよく分からないという声が少なくありません。
実際、BIOSのアップデートにはメリットもあればリスクもあるため、正しい知識をもって判断することが重要です。本記事では、BIOSとは何かという基本から、アップデートが本当に必要なタイミング、そして各メーカー別の具体的な手順までを詳しく解説します。
BIOSとは?
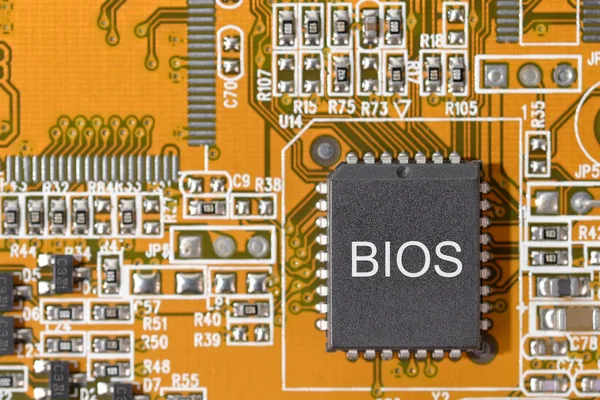
パソコンを構成するさまざまな部品が正常に動作するためには、それらを管理・制御する仕組みが必要です。そこで重要な役割を担っているのが「BIOS(バイオス)」です。
BIOSとは「Basic Input/Output System」の略で、マザーボードに内蔵されている小さなファームウェアのことを指します。電源を入れた際、最初に動作してハードウェアの状態をチェックし、OS(Windowsなど)を立ち上げる準備を行います。つまり、BIOSがなければパソコンは起動しないのです。
BIOSは設定画面から起動順序の変更やハードウェアの管理ができ、対応機種によってはCPUの動作を微調整する「オーバークロック」なども行えます。また、近年ではBIOSの後継として「UEFI(ユーイーエフアイ)」と呼ばれる仕組みも一般化していますが、基本的な役割は同じです。BIOSは普段はあまり意識する機会がないものの、安定したパソコン環境を維持するうえで欠かせない存在といえるでしょう。
BIOSにアクセスする方法を解説!

BIOSの設定を確認・変更するためには、まずBIOSにアクセスしなければなりません。通常、BIOSはWindowsなどのOSが起動する前の段階でしか操作できません。そのため、パソコンの電源を入れた直後に、特定のキーを押してBIOS画面に入る必要があります。
アクセスに使用するキーはメーカーやモデルによって異なりますが、一般的には「Del」キーや「F2」キーが多く採用されています。中には「F1」「F10」「Esc」キーが割り当てられている場合もあるため、事前に取扱説明書やメーカー公式サイトを確認しておくと安心です。
キーを押すタイミングは、電源を入れてすぐのロゴ表示中です。このとき画面の下部に「Press F2 to enter Setup」や「Press Del to enter BIOS」といった表示が出ることもあります。タイミングを逃すとそのままWindowsが起動してしまうため、電源を入れてすぐに対象のキーを数回押すのが確実です。
BIOSにアクセスすると、キーボード操作で設定画面が表示されます。ここでは起動ドライブの優先順位や日時の設定、ハードウェアの状態確認などが行えます。
BIOSアップデートする前に!バージョンを確認する方法を解説

BIOSアップデートを行う前に、現在使っているBIOSのバージョンを必ず確認しましょう。バージョン確認の方法はいくつかありますが、代表的なのはBIOS設定画面で直接見る方法と、Windowsのシステム情報から確認する方法です。
まず、BIOS設定画面に入るにはパソコン起動時に特定のキーを押してBIOS画面にアクセスします。画面のトップページや情報タブに「BIOS Version」や「Firmware Version」といった表記があり、そこに現在のバージョン番号が記載されています。
次に、Windows上から確認する方法もあり、スタートメニューの検索ボックスに「msinfo32」と入力してシステム情報を開いてみましょう。表示される画面の中に「BIOS バージョン/日付」という項目があり、ここで現在のBIOSバージョンとリリース日が確認できます。
コマンドプロンプトを使う方法もあり、コマンドプロンプトを開き、「wmic bios get smbiosbiosversion」と入力すると、BIOSのバージョンが表示されるはずです。どの方法で確認してもよいですが、必ずメーカーの公式サイトで最新のBIOSバージョンと照合し、アップデートが必要かどうかを判断してください。
BIOSアップデートは必要?適切なタイミングを解説
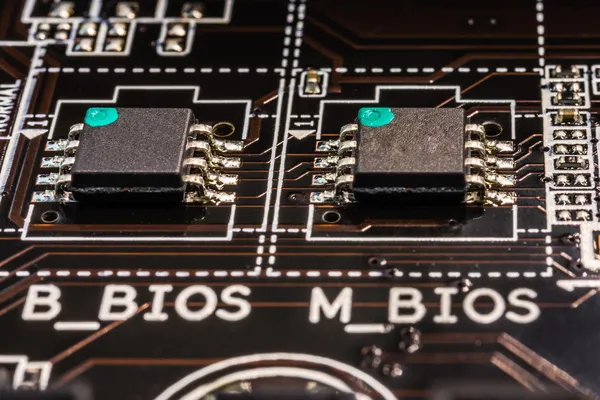
パソコンのBIOSアップデートは、正しいタイミングで行えば性能や安定性の向上に役立ちますが、むやみに行うとトラブルの元にもなります。
ここでは、BIOSアップデートが本当に必要かどうか、その判断基準と適切なタイミングについて詳しく解説します。アップデートのメリットとリスクを理解し、安全に作業を進めるためのポイントをおさえていきましょう。
BIOSアップデートは必要なのか
BIOSアップデートは、パソコンの安定性や機能を向上させるために重要な作業ですが、すべてのユーザーが必ず実施すべきというわけではありません。というのも、BIOSの更新にはリスクも伴い、失敗するとパソコンが起動しなくなる可能性があるからです。
一方で、BIOSアップデートは新しいハードウェアへの対応や既知の不具合修正、セキュリティの強化などに役立ちます。例えば、新しいCPUやメモリを追加したい場合、それらに対応するためのBIOSアップデートが提供されることがあります。また、特定のバグが原因で起動時のエラーや不安定な動作が起こっているときも、アップデートで改善されるケースが多いです。
近年はサイバー攻撃の高度化に伴い、BIOSに対するセキュリティパッチが公開されることも増えています。とはいえ、すべてのアップデートが必須というわけではないので、更新内容をよく確認し、自分の環境に必要なものであれば実施するのが賢明です。
つまり、BIOSアップデートは「問題がある場合」や「新しい機能や対応が必要な場合」に限って行うべきであり、普段は安定しているなら無理に手を加える必要はありません。正しい判断をするためにも、メーカーの公式情報を必ずチェックしてから行動しましょう。
アップデートすべきタイミング
BIOSアップデートを行うべきタイミングは、主にいくつかのケースに分けられます。まず一つ目は、新しいハードウェアを導入したときです。
例えば、新しいCPUやメモリ、ストレージを搭載した場合、既存のBIOSがそれらのハードウェアに対応していないことがあります。このとき、メーカーが提供する最新のBIOSにアップデートすることで、正常に動作させることが可能になります。
二つ目は、パソコンの動作が不安定になったり、起動時にエラーが発生するなどトラブルが起きた場合です。こうした不具合はBIOSのバグや不具合が原因であることがあり、アップデートによって問題が改善されるケースがあります。
三つ目は、メーカーが重要なセキュリティアップデートを配布した場合です。BIOSにも脆弱性が発見されることがあり、それを悪用されるリスクを防ぐために更新が必要になることがあります。セキュリティ関連のアップデートは早めに適用することが推奨されているため、こまめにメーカーの情報をチェックしましょう。
BIOSをアップデートする方法をメーカー別に解説!

BIOSアップデートの手順はメーカーによって異なります。ここでは代表的なDell、HP、富士通、ASUSの4社を例に、それぞれのアップデート方法をわかりやすく解説します。
どのメーカーも公式サイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、専用ツールを使ってアップデートを行うのが基本です。安全に作業を進めるためのポイントも合わせて紹介します。
Dell
DellのパソコンでBIOSをアップデートするには、まずDellの公式サポートサイトにアクセスします。ここで自分のパソコンのサービスタグ(製品識別番号)を入力し、機種に合った最新のBIOSアップデートファイルを探しましょう。
アップデートファイルは通常、実行形式(.exe)のプログラムになっているので、ダウンロード後にダブルクリックで起動します。作業中は電源を絶対に切らないようにし、ノートパソコンの場合は必ずACアダプターを接続してください。アップデートが完了すると自動で再起動し、新しいBIOSが適用されます。
また、Dellは「SupportAssist」という専用ツールを提供しており、これを利用するとBIOSやドライバーのアップデートを一括管理できるので便利です。トラブル防止のために、作業前に重要なデータのバックアップを忘れずに行いましょう。
HP
HPのパソコンでは「HP Support Assistant」を使ってBIOSのアップデートが可能です。公式サイトで製品名やシリアル番号を入力して、最新のBIOSアップデートが提供されているか確認しましょう。
アップデートファイルはインストーラー形式で提供され、多くの場合、実行すると再起動後に自動的に更新作業が始まります。USBメモリを使ったアップデート方法も用意されており、OSが起動しない場合の緊急対応として役立ちます。
作業中は電源が切れないように注意し、特にノートPCはACアダプターを接続して行いましょう。HPの公式サポートには詳細な手順書もあるので、不安な方はそちらを参照するのがおすすめです。アップデート前にはデータのバックアップを必ず行ってください。
富士通
富士通のパソコンでは、「アップデートナビ」という専用アプリを使ってBIOSのバージョン確認やアップデートができます。
多くの機種では自動的にアップデートの通知が届き、ワンクリックで更新できますが、古い機種や法人モデルなど手動で行う必要がある場合は、富士通の公式サイトから対象機種のBIOSアップデートファイルをダウンロードしてください。
インストール手順に従って進めると、再起動時にBIOSのアップデートが実行されます。更新中は絶対に電源を切らず、ノートPCならACアダプターを必ず接続しておきましょう。富士通は日本メーカーなので、サポートも日本語で手厚く安心して利用できます。
ASUS
ASUSのマザーボードでは、「EZ Flash」ユーティリティというBIOSアップデートツールが標準搭載されています。
まずASUSの公式サイトで自分のマザーボードの型番を検索し、最新のBIOSファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファイルをUSBメモリに保存し、BIOS設定画面の「Tool」タブから「EZ Flash Utility」を起動しましょう。画面の案内に従いUSB内のBIOSファイルを選択すると、アップデートが開始されます。
作業中は絶対に電源を切らないようにし、完了後は自動的に再起動して新しいBIOSが有効になります。ASUSの方法はBIOS内から直接アップデートできるため、比較的安全かつ便利です。ただし、USBメモリのフォーマットやファイル名に注意し、誤ったファイルを選ばないよう気をつけてください。
BIOSをアップデートする際の注意点とは?

BIOSアップデートはパソコンの安定性や機能を改善する重要な作業ですが、慎重に行わなければ重大なトラブルにつながる可能性があります。
まず、アップデート中に電源が切れることは絶対に避けてください。処理が途中で止まると、BIOSが破損しパソコンが起動しなくなるリスクが高まります。アップデートに使用するファイルは必ずメーカー公式サイトからダウンロードし、自分の機種と型番に一致するバージョンであることを必ず確認してください。間違ったBIOSをインストールすると、システムに深刻な障害が発生する可能性があります。
さらに、BIOSアップデートの前には現在のBIOSバージョンを確認し、アップデートが本当に必要であるかを判断しましょう。アップデートが必要な場合でも、作業前には重要なデータのバックアップを必ず取っておくことをおすすめします。通常はBIOS更新でデータが消えることはありませんが、万一のトラブルに備えるためです。
最後に、アップデート手順はメーカーごとに異なるため、必ず公式の手順書やガイドに従って慎重に進めることが重要です。焦らず、落ち着いて作業を行い、万が一のトラブル時には専門の修理業者やメーカーサポートに相談するのが安心です。
まとめ BIOSアップデートにお困りの方は横浜市のパソコン修理プロセンターへ

BIOSアップデートはパソコンの性能や安全性を維持するために重要ですが、作業にはリスクも伴います。自信がない場合やトラブルが心配な方は、専門のプロに任せるのがおすすめです。
横浜市にある「パソコン修理プロセンター」では、BIOSアップデートをはじめ、さまざまなパソコンのトラブルに対応しています。店舗を構えず出張専門で行っているため、最短で即日修理が可能・かつ質の高いサービスを格安で提供しています。豊富な経験と知識を持つスタッフが訪問するので、あらゆるトラブルへの対応力も抜群です。
神奈川県内のほか、関東エリア(東京都&埼玉県&千葉県など)も相談可能です。詳しい情報は下記公式サイトをご覧ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 修理メニュー2025年12月19日川崎近辺でパソコン修理を頼むならどこ?選び方やおすすめの店舗を紹介!
修理メニュー2025年12月19日川崎近辺でパソコン修理を頼むならどこ?選び方やおすすめの店舗を紹介! 修理メニュー2025年11月10日横浜でのパソコン修理の料金相場はいくら?安く抑えるコツを徹底解説!
修理メニュー2025年11月10日横浜でのパソコン修理の料金相場はいくら?安く抑えるコツを徹底解説! 修理メニュー2025年11月5日横浜でパソコン修理するならどこがいい?失敗しない業者選びのポイントを徹底解説!
修理メニュー2025年11月5日横浜でパソコン修理するならどこがいい?失敗しない業者選びのポイントを徹底解説! 修理メニュー2025年10月13日パソコン修理の値段相場はいくら?安く直すコツと依頼先の選び方を解説!
修理メニュー2025年10月13日パソコン修理の値段相場はいくら?安く直すコツと依頼先の選び方を解説!